新しい生活を始めるワクワク感とは裏腹に、引っ越し後に「隣の音がうるさい」「上の階の足音が響く」といった騒音トラブルに悩まされる人は少なくありません。
一度住んでしまうと簡単に引っ越すこともできず、ストレスが積み重なる一方です。
しかし、物件選びの段階で気をつけておけば、多くの騒音リスクは回避できます。
この記事では、騒音トラブルの原因を知り、内見や契約時にどうチェックすべきかを詳しく解説。
快適な新生活のための実践的な物件選びのコツを紹介します。
第1章:そもそも騒音トラブルとは?

騒音トラブルとは、生活音や外部音が原因で、日常生活に不快感や支障を感じる状態のことです。
● よくある騒音の種類
- 生活音:足音、ドアの開閉音、トイレや水道の音、テレビ・音楽
- 外部音:車・バイクの走行音、近隣店舗や工事の音、線路の走行音
- 建物特有の音:配管の水流音、エレベーターの作動音など
● 苦情になりやすい音トップ3
- 上階の足音:特に子どもがいる家庭では走り回る音が問題に
- 隣人の話し声・テレビ音:壁が薄い場合は普通の会話も筒抜けに
- 外からの騒音:深夜の車・バイク音や飲食店の営業音など
音に対する感じ方は個人差が大きく、本人にとっては耐えられない音でも、相手には気づかれていないケースが大半です。だからこそ、未然の対策が重要です。
第2章:物件選びで注目すべきポイント

● 建物構造は騒音対策の基本
- RC造(鉄筋コンクリート)は、音の遮断性が最も高い。
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート)も同等かそれ以上の防音性能。
- 一方で木造・軽量鉄骨造は、壁が薄く、生活音が響きやすい傾向あり。
「予算的に木造しか無理…」という場合でも、後述のチェックポイントで防げるリスクもあります。
● 間取りと部屋の位置も大事
- 角部屋は隣接する部屋が少なく、生活音の影響が減る。
- 最上階は上からの足音に悩まされずに済む。
- エレベーターや階段の真横、ゴミ置き場の近くは、利用者の話し声や足音が集中しやすいため注意。
● 住人層や物件タイプにも注目
- 学生向け物件やペット可物件は、活動音が大きくなりがち。
- ファミリー向けは子どもの足音や泣き声の可能性あり。
- 築浅マンション=静かとは限らない。構造や住民次第。
第3章:内見時に確認すべきこと
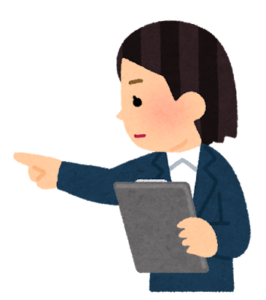
物件を訪れたときにできる、騒音チェックの実践ポイントです。
● 可能なら「静かな時間帯」にも訪問を
- 平日昼間の内見では、住人が不在で音の確認ができないことも。
- 夕方~夜、土日の内見が可能なら、その時間帯に現地に行くと実態がわかりやすい。
● 壁・床・窓の“響き方”をチェック
- 壁を軽くノックしてみる:空洞音が響くなら、防音性は低め。
- 窓を閉めた状態で外の音が聞こえるか:遮音性の目安になる。
- フローリングの「きしみ」や「反響」も要注意。
● 共用スペースも意外な騒音源
- 廊下や階段の音が響く構造は、部屋の中にも音が伝わりやすい。
- 集合ポストの前や駐輪場近くは、会話や音の発生源になりやすい。
第4章:事前にできる調査・確認方法

内見以外でも、騒音リスクを探る手段はいくつかあります。
● インターネット検索・レビュー確認
- マンション名や住所で「騒音」「うるさい」「トラブル」などのキーワードを入れて検索。
- 不動産サイトのレビュー欄、Googleマップのクチコミも意外と参考になる。
● ストリートビューで周辺環境を確認
- 飲食店、コンビニ、道路の交通量、学校、工場、線路などをチェック。
- 昼と夜で雰囲気が違うエリアも多いので、現地に行けないときほどストリートビューによる検索が有効。
● 管理会社・不動産会社へのヒアリング
- 「この物件で騒音の苦情があったことはありますか?」と率直に聞いてOK。
- クレーム履歴がある物件の場合、聞かれたら答える義務があります(但し回答を濁すケースも)。
第5章:引っ越し後のトラブルを避けるために

● 騒音トラブルが起きたときの対処法
- まずは管理会社や大家へ相談。直接相手に言うのは避けた方が無難。
- トラブルの記録(日時、内容)を残しておくと、交渉しやすくなる。
● 自分でできる防音・緩和対策
- 防音カーテン・防音マット・スリッパの使用で音を吸収
- テレビや音楽のボリューム管理は自分の防衛策にもなる
- 夜間の掃除機・洗濯機・入浴音は、特に気をつけたい
● 自分自身が“音の出し手”になるリスクも意識
- 上下左右に人が住んでいることを忘れない
- 引っ越し初日は特に、静かに過ごすのが印象としても◎
まとめ
騒音トラブルは、目に見えない分、軽視されがちですが、実際には引っ越し後の満足度を大きく左右するポイントです。
- 建物構造や部屋の位置、住人層を見極める
- 内見では「音のチェック」を忘れずに
- 契約前にネットや不動産会社でのリサーチを
- そして自分自身も、音に配慮した生活を心がける
快適な新生活を実現するために、「音」の問題を物件選びの基準にしっかり組み込んでいきましょう。